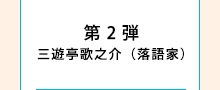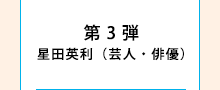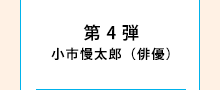モデルとして活躍し、“きれいで優しいお母さん”のイメージがぴったりのいつこさん。CMなどでは、俳優さんと共演することも。だが、ソフトテニスをプレーしていたころの彼女は、お嬢様学校に通いながらも、スポ根マンガのような生活を送っていた。
「母が松蔭出身ということもあり、娘を松蔭に入れたかったようなんです」
小学3年から6年まで地元・神戸の少年野球チームに所属する活発な少女だった。足が速く、肩も強く、そして何よりも負けず嫌い。そんな彼女が中学受験をし、お嬢様学校として有名な松蔭中の門をたたいた。
「クラブ活動を決めるとき、たまたま友だち3人とソフトテニス部を見学したんですね。それがきっかけです。1年生50人程度が入部したのですが、1年生が終わるころには8人に、そして3年のころには3人になっていました」
友だちに勧められ、入部したソフトテニス部。周囲からは『せっかく松蔭に入学したのに、なぜ、入ってはいけない部に入ったんだ』と言われていた。お嬢様学校にありながら、そのイメージとは真逆の厳しさがハンパない部活だったからだ。
「抜けられなかったですね。でも、中学3年の終わりに、『高校からは違う人生を歩みたい』と思って退部届を顧問の吉村知広先生に出したんです。そうしたら、先生が退部届を破ってしまって(笑)」
「母が松蔭出身ということもあり、娘を松蔭に入れたかったようなんです」
小学3年から6年まで地元・神戸の少年野球チームに所属する活発な少女だった。足が速く、肩も強く、そして何よりも負けず嫌い。そんな彼女が中学受験をし、お嬢様学校として有名な松蔭中の門をたたいた。
「クラブ活動を決めるとき、たまたま友だち3人とソフトテニス部を見学したんですね。それがきっかけです。1年生50人程度が入部したのですが、1年生が終わるころには8人に、そして3年のころには3人になっていました」
友だちに勧められ、入部したソフトテニス部。周囲からは『せっかく松蔭に入学したのに、なぜ、入ってはいけない部に入ったんだ』と言われていた。お嬢様学校にありながら、そのイメージとは真逆の厳しさがハンパない部活だったからだ。
「抜けられなかったですね。でも、中学3年の終わりに、『高校からは違う人生を歩みたい』と思って退部届を顧問の吉村知広先生に出したんです。そうしたら、先生が退部届を破ってしまって(笑)」
毎日毎日、練習が続く。しかし、それでも続けたのは、厳しい練習にともに耐えた仲間の存在と、試合で勝ち、成果が出ていたからだった。藤田未彩子(ふじた・みさこ)さんとのペアで、高3ではインターハイ3位入賞。
「私はO型なんですが、藤田さんはマイペースなB型。私が試合前にプレッシャーで弱気になると、彼女によく振り向きざまに殴られました。これ、本当なんですよ。あるときなんて、ドブ川に突き落とされましたし(笑)」
後衛だったいつこさんは体も細く、スピードボールで押し込むタイプではなく、配球勝負の選手。一方の藤田さんは、というと…。
「現在、グレーダー(服の原型となる型紙を制作するスペシャリスト)でもある藤田さんですが、当時からアーティストでした(笑)。動きが独特。野性的でセオリーがない!」
いつこさんと藤田さんは中・高と6年間ペアを組んだ。タイプがまったく異なったものの、本音で、本気で、向き合った2人。だからこそ、強い信頼関係で結果を残した。その結果も評価され、いつこさんは学内進学をし、表孟宏監督(現・日本ソフトテニス連盟会長)率いる名門・松蔭女子学院大ソフトテニス部へ。しかし、藤田さんは夢でもあったデザイナーの学校へ進み、テニスもやめた。
「通常、松蔭高から大学のソフトテニス部には選手は入れないんですね。ただ、私はインターハイで結果を残せたので。だから、同級生7名も皆、全国大会で活躍した選手ばかり。とにかくプロ集団という感じでした」
大学女子を牽引してきた松蔭女子学院大。特に、いつこさんが在籍した時代はインカレ連覇のほか、全日本選手権、全日本シングルス選手権で松蔭の選手たちは上位進出。日本のソフトテニス界を牽引する存在でもあった。特に、いつこさんが大学3年だった1995年阪神淡路大震災に見舞われ、大学も被災。コートが使えないなか、九州・佐賀で合宿を行っていた。「日本一になって恩返しを。神戸を元気にしたい」という言葉を胸に、皆でインカレ日本一をもぎ取った。
「私はO型なんですが、藤田さんはマイペースなB型。私が試合前にプレッシャーで弱気になると、彼女によく振り向きざまに殴られました。これ、本当なんですよ。あるときなんて、ドブ川に突き落とされましたし(笑)」
後衛だったいつこさんは体も細く、スピードボールで押し込むタイプではなく、配球勝負の選手。一方の藤田さんは、というと…。
「現在、グレーダー(服の原型となる型紙を制作するスペシャリスト)でもある藤田さんですが、当時からアーティストでした(笑)。動きが独特。野性的でセオリーがない!」
いつこさんと藤田さんは中・高と6年間ペアを組んだ。タイプがまったく異なったものの、本音で、本気で、向き合った2人。だからこそ、強い信頼関係で結果を残した。その結果も評価され、いつこさんは学内進学をし、表孟宏監督(現・日本ソフトテニス連盟会長)率いる名門・松蔭女子学院大ソフトテニス部へ。しかし、藤田さんは夢でもあったデザイナーの学校へ進み、テニスもやめた。
「通常、松蔭高から大学のソフトテニス部には選手は入れないんですね。ただ、私はインターハイで結果を残せたので。だから、同級生7名も皆、全国大会で活躍した選手ばかり。とにかくプロ集団という感じでした」
大学女子を牽引してきた松蔭女子学院大。特に、いつこさんが在籍した時代はインカレ連覇のほか、全日本選手権、全日本シングルス選手権で松蔭の選手たちは上位進出。日本のソフトテニス界を牽引する存在でもあった。特に、いつこさんが大学3年だった1995年阪神淡路大震災に見舞われ、大学も被災。コートが使えないなか、九州・佐賀で合宿を行っていた。「日本一になって恩返しを。神戸を元気にしたい」という言葉を胸に、皆でインカレ日本一をもぎ取った。
中学で一から始めたソフトテニスだったが、どんなにつらくても、結局、高校、そして大学では全国の精鋭たちと切磋琢磨し続けた。
「実は、私、高3のインターハイ準決勝で負けたときの夢を今も見るんです。あと1本で勝てるというときに、私は『華々しく決めてやろう』と逆クロスのストレートに打ち込んだんです。だけど、それが外れ、そこから大きく崩れていった。ゲーム・カウント3-1からの劇的な逆転負け。自分自身、『やっちまった』という罪悪感でいっぱいになりました。やってはいけないことをやってしまった。監督は何も言いませんでしたけど、あのときのことは、一生忘れない。あのときの一球が、大学でもソフトテニスを続けた原動力になっていたと思います」
「実は、私、高3のインターハイ準決勝で負けたときの夢を今も見るんです。あと1本で勝てるというときに、私は『華々しく決めてやろう』と逆クロスのストレートに打ち込んだんです。だけど、それが外れ、そこから大きく崩れていった。ゲーム・カウント3-1からの劇的な逆転負け。自分自身、『やっちまった』という罪悪感でいっぱいになりました。やってはいけないことをやってしまった。監督は何も言いませんでしたけど、あのときのことは、一生忘れない。あのときの一球が、大学でもソフトテニスを続けた原動力になっていたと思います」
決して体力があったわけでもない。球が速いわけでもなかった。だから、1球でも少なく、効率よく配球することをずっと考えてきたという。パワーヒッターと相対すれば、強打させない球を先に打つ。「野球でたとえれば、サイドスローのピッチャーというイメージ」といつこさん。高2のときにグリップがズレたことも奏功。周囲からは『どの面で打っているのか分からない』と言われるほどの超ウエスタンだったが、そのどの面で打つのかが分からないことで唯一無二のプレーヤーになれた。相手を存分に惑わせ、勝利へとつながった。
「グリップが変わっていなかったなら、勝ててはいなかった。グリップが変わったから勝ち続けたんだと思います」

大学卒業後は商社へ就職。「普通の女の子に戻りたい」と表監督に伝えて、一般企業への就職の道を選んだ。大阪の会社へ自宅から通い、OLとしての生活が始まった。その後、25歳で結婚、27歳で長男を出産。
「29歳のときに、夫の転勤で東京に来ました。子どもの幼稚園で出会った方が、実はモデル業界の方で、『やってみない』と声を掛けられたんです。その出会いがあって、モデルになったのですが、子どもを産んで、それも30歳のデビューだったんですよね」
ご両親には反対されたが、多くの人の前でパフォーマンスをすることには快感を覚えた。それは、ソフトテニス・プレーヤーとして経験してきたことと同じだった。
「フィールドは違うけれど、チャンスがあれば挑戦したいという気持ちになりました。徐々に家族も理解してくれるようになりました。ただ、スタートがとにかく遅いですから、正直、引け目を感じることもありました。でも、テニスをしてきたことで気持ちの強さを持ち合わせていた。だから、今の仕事で挫折を感じたことはありません。今はつらい状況があったとしても、しんどさは2割。だから、そのしんどさも楽しい。やはり、テニスをしていたときが一番つらかったから(笑)。心がダメという状況になったとしても、体が立っていられたら心も大丈夫」 オーデションに落ちたときは、試合に負けたときの感覚に似ているという。しかし、そこから気持ちを立て直し、切り替えができるのは、テニスをやっていたからこそ。
「中学・高校・大学とソフトテニスを続けて得たものが、今のモデルという仕事に生きているんですよね」 新たなフィールドで颯爽とした姿を見せるいつこさん。何千本、何万本と白球を打ち続けてきた、その一つひとつの経験が血となり、肉となっている。
「29歳のときに、夫の転勤で東京に来ました。子どもの幼稚園で出会った方が、実はモデル業界の方で、『やってみない』と声を掛けられたんです。その出会いがあって、モデルになったのですが、子どもを産んで、それも30歳のデビューだったんですよね」
ご両親には反対されたが、多くの人の前でパフォーマンスをすることには快感を覚えた。それは、ソフトテニス・プレーヤーとして経験してきたことと同じだった。
「フィールドは違うけれど、チャンスがあれば挑戦したいという気持ちになりました。徐々に家族も理解してくれるようになりました。ただ、スタートがとにかく遅いですから、正直、引け目を感じることもありました。でも、テニスをしてきたことで気持ちの強さを持ち合わせていた。だから、今の仕事で挫折を感じたことはありません。今はつらい状況があったとしても、しんどさは2割。だから、そのしんどさも楽しい。やはり、テニスをしていたときが一番つらかったから(笑)。心がダメという状況になったとしても、体が立っていられたら心も大丈夫」 オーデションに落ちたときは、試合に負けたときの感覚に似ているという。しかし、そこから気持ちを立て直し、切り替えができるのは、テニスをやっていたからこそ。
「中学・高校・大学とソフトテニスを続けて得たものが、今のモデルという仕事に生きているんですよね」 新たなフィールドで颯爽とした姿を見せるいつこさん。何千本、何万本と白球を打ち続けてきた、その一つひとつの経験が血となり、肉となっている。
Text by Yoko YAGI 八木陽子
Photo BY Seiko KANASHIRO 金城聖子
Photo BY Seiko KANASHIRO 金城聖子