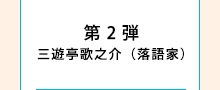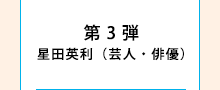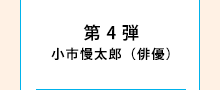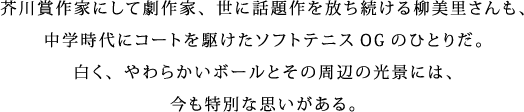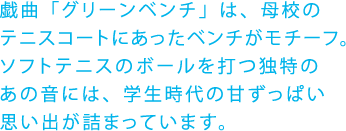
「本当の名前は地蔵坂って言うんですけど。丘の上は、フェリス・横浜雙葉・横浜共立という『神奈川女子御三家』と呼ばれるミッション系女子校の密集地帯で、朝は各校の制服で坂道が埋め尽くされるから、乙女坂」
坂の上にある女子校のテニスコートは通りに面していて、女子部員のボールを打つ音が響く。母親はその脇を通るたび、「美里も大きくなったらここでテニスをするのよ」と言い聞かせた。
「私が通っていたのは、歴史の古さでは日本で五指に入る女子校でした。学校の正面にハードコート2面が並んでいて、部員がテニスをする姿が生垣越しに見えるんです。コートの一角にはグリーンベンチと呼ばれるベンチが、明治4年の創立以来、ずっと置かれている。グリーンベンチは、学校の象徴のような存在でした。私の母はそのテニスコートに強い思い入れをいだいていて、学校とソフトテニスがセットで、母が私に託す夢になっていた」
母親の夢を叶えるべく、小学6年から進学塾に通って合格した中高一貫教育の女子校、部員100人がひしめくコートで、ラケットを握ることになった。
「合格が決まって、母は涙を流したり小躍りしたりして大喜びしました。ラケットももう、好きなの買いなさい!みたいな大盤振る舞い。私も気が大きくなって、ヨネックスの、上級者用の2万円以上するラケットを選びました」
「上級生はスコート姿。中学1、2年生はえんじ色のジャージでボール拾い。素振りも延々とやりました」
「当時は80年代アイドル全盛の時代で、高校の先輩たちはみんなサイドをゆるくカールさせた聖子ちゃんカット。その髪とスコートが、スイングする度にフワッ、ヒラッと揺れる――憧れましたね」
「ラインの外にボールが飛んでくると、1、2年生どうし競うようにダッシュです。コートの縁に木や花が植えられていて、その土の部分にボールが入ってはいけない決まりだったんです」
「ソフトテニスって、独特の間がありますよね。ボールに緩急がある。バウンドしてすぐに打つこともあれば、かなり引きつけて、(一拍)ッポーンと打つこともある。私たちジャージ組は、先輩が打つそのリズムに合わせて『ソレ!』『……ソーレ』って声を掛けて」
「早朝、まだ暗いうちに家を出て、電車に乗って、乙女坂を上って、先輩たちが登校する前にコート整備を済ませるのが、下級生の仕事でした」
練習は、教会に行かなければならない日曜以外は毎日あった。夏休みも休まず活動する部だった。雨が降ると体育館のスロープを走った。
「部活の花形といえばソフトテニス、バスケ、バレーボール。校則はとても厳しくて、コート、レインコート、靴下まで学校で指定されたもの以外は禁止でした。ただテニス部は、学校で一番目立つ、外に面した場所(コート)が舞台で、かわいいテニスウエアーを着て――ある意味、私服ですよね――後輩たちの熱い視線を全身に浴びてプレーする!テニス部のコートは、学校でいちばん自由度が高い場所だったんです」

「高校1年の年に、辞めてしまったので。退学届を出して、学校を出ていくときの光景は今でもはっきり覚えていますね。グリーンベンチが右手にあって、左にコート。コートにも校庭にも生徒はいなかった。桜が散る季節でした。横浜市の指定有形文化財の洋館である本校舎3階の音楽室から、讃美歌の歌声が響いていました」
15歳で、慣れ親しんだベンチを背にして挑んだのが、演劇の世界だった。翌年、ミュージカル劇団『東京キッドブラザース』に役者として入団。戯曲、小説と、現在の道に至る大きな決断となる。
「ソフトテニス部で上下関係が厳しい体育会系の人間関係に慣れていたので、劇団内の先輩後輩の関係に抵抗をおぼえることはありませんでしたね」
1994年に書いた戯曲、「Green Bench(グリーンベンチ)」は、ソフトテニスをモチーフにしている。役者は全編、ラケットを手に、ラリーをしながらセリフを飛び交わせる。母と娘の葛藤を描いた物語には、自分と母親との関係が投影されている。 「母の強い希望で入った学校だったんですが、やはり人は、他人の夢の中では生きられない。この舞台は、本
当は実際にボールを打ちながらやりたかったんです。だけど、もしボールが客席に行ってしまったら、とかいろいろ考えて断念。スイングに合わせて、ソフトテニスのボールの音をかぶせました。あのパコーン、パコーンという音、独特ですよね」

今でも、柳さんの耳にははっきりとボールの音が残っている。
「息子が私が高校を退学した15歳になって、自分の15歳の時を思い返すようになりました。もうちょっとがんばって学校に残っていればよかったな、と悔やむことがあるんですよ。夢を見るんです、ソフトテニスの夢。今までインタビューを受けても聞かれたことはなかったし、ソフトテニスについては自分でも封印していたようなところがあるんですが、最近は、少しずつ封がはがれてきている感じですね。やはり、途中で辞めたものって念が残るじゃないですか。私の場合はボールの音が夢に出てくる。『案山子とラケット』の予告編も、ボールの音から始まりますよね。そして、風、水たまり、湧き上がる雲の映像……。ボールの音が呼び水となって、懐かしい風景がよみがえる。ソフトテニスほど自然と響き合うスポーツも珍しい。まあ、あれほど風の影響を受ける競技もないでしょうからね」
球拾いしながら見た真夏の青空、汗だらけの顔を吹き抜けていった風の感触、声を合わせた部員たちの掛け声、すべてはボールの音とともによみがえってくるという。
「人が死ぬときって、走馬灯のように思い出が浮かぶって言いますよね。私は、きっとグリーンベンチやテニスボールやコートに舞い散る桜を見ると思う。ひとことで言うと、青春ですね。振り返ってみないと、見えないもの。私は、青春の真っ盛りでいち抜けて、振り返って懐かしむ暇もなく、30年間書きつづけてきました。ボールの音には、青春時代のすべてが詰まっています」
副部長のツカダ先輩が好きだった!と女子校の中学生らしい思い出も披露した柳さん。実はいま、「高卒認定試験を受け、大学に行く」という目標を持っている。
「そのときは、入りたいな、ソフトテニス部。こんな年齢の新入生が来たら、みんなびっくりしますかね」
今度は好きなウエアーを選んで、参りましょうか。
Photo by Hideo Ishibashi