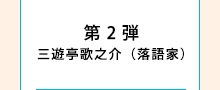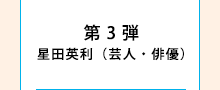役柄によって幅広く変わる貌(かお)――数多くのドラマ、映画、CMに出演する役者、小市慢太郎さんはインタビューのあいだ、終始やわらかく笑っていた。中学、高校と名門ソフトテニス部に所属し、高校時代は全国大会でベスト8。白球、そして仲間とともに青春を過ごした小市さん、ソフトテニスの映画をつくると聞いての第一印象は――。
「懐かしかったですね。そして、うれしかった。自分がやっていた競技ですから、やはり。ホン(脚本)を読ませてもらったとき、率直に、これは素敵な、いい話だと感じました。山、田んぼ、動物たち、村の人々がいて、コートができる。撮影で佐渡に入ったときも、いいところだなあ と」
撮影ロケ地となった新潟県・佐渡島でのこと。撮影前日の晩に佐渡に入った小市さんのもとに、一本の電話が入った。それはスタッフを通じ、共演の星田英利さんから入った、お酒のお誘いで--。
「近くのスナックで、お互い初対面ですから『初めまして』からの会話だったんですが、翌日の撮影の話から始まって、星田さんはずっと映画、演技の話。もう質問責めですよ。芝居に対する思いが熱くて、真面目で、ああ、この人は『青木さん』(星井さんの役)だなあと。 初日の前夜からそんなふうだったので、撮影の終盤は感慨深いものがありました。一人ひとり違う人たちがいて、それぞれに思いを抱えていて。中学生たちの情熱が周りを引っ張って、人々の意識が変わっていく物語。撮影の現場と作品とが重なっていく感覚がありました」 映画のラストに近いシーン、主人公・亜季(平祐奈)と父親役・小市さんとの場面は、撮影においても終盤だった。
「平さんについては、撮影を終えて、かわいい人やなあ、とあらためて感じました。人としてかわいい、というのか。思いが真っすぐで、素敵な女優さんで、僕は今回、彼女からもいろんなものをもらいました。父親役としては、とてもありがたかった。最後の撮影では、娘・亜季としての達成感と、平祐奈ちゃん自身の姿が重なって、自然とこみ上げるものがありました」
「懐かしかったですね。そして、うれしかった。自分がやっていた競技ですから、やはり。ホン(脚本)を読ませてもらったとき、率直に、これは素敵な、いい話だと感じました。山、田んぼ、動物たち、村の人々がいて、コートができる。撮影で佐渡に入ったときも、いいところだなあ と」
撮影ロケ地となった新潟県・佐渡島でのこと。撮影前日の晩に佐渡に入った小市さんのもとに、一本の電話が入った。それはスタッフを通じ、共演の星田英利さんから入った、お酒のお誘いで--。
「近くのスナックで、お互い初対面ですから『初めまして』からの会話だったんですが、翌日の撮影の話から始まって、星田さんはずっと映画、演技の話。もう質問責めですよ。芝居に対する思いが熱くて、真面目で、ああ、この人は『青木さん』(星井さんの役)だなあと。 初日の前夜からそんなふうだったので、撮影の終盤は感慨深いものがありました。一人ひとり違う人たちがいて、それぞれに思いを抱えていて。中学生たちの情熱が周りを引っ張って、人々の意識が変わっていく物語。撮影の現場と作品とが重なっていく感覚がありました」 映画のラストに近いシーン、主人公・亜季(平祐奈)と父親役・小市さんとの場面は、撮影においても終盤だった。
「平さんについては、撮影を終えて、かわいい人やなあ、とあらためて感じました。人としてかわいい、というのか。思いが真っすぐで、素敵な女優さんで、僕は今回、彼女からもいろんなものをもらいました。父親役としては、とてもありがたかった。最後の撮影では、娘・亜季としての達成感と、平祐奈ちゃん自身の姿が重なって、自然とこみ上げるものがありました」
小市さんが中学から入学した大阪の私立校・明星学園中高は、昭和41年から44年まで(1966-1969年)インターハイ団体4連覇(男子ではいまだに最多連覇記録)も遂げた名門。小市さんは6年間、ソフトテニス部に所属した。
「中1で入部してテニスを始めました。初めは指導も優しいし、楽しい部活なのですけど、上達するにしたがって、要求は厳しく、練習はしんどくなっていった。僕ら、府予選前にやる大会で、同じ地区に上宮がいたんです。大会ごと必ず当たるので、お互いに名前も、プレーのクセも完全に覚えて戦っていました」
インタビューを受ける小市さんの手元には、取材資料であるソフトテニス・マガジンの記録ページが置かれていた。
「ここ『上宮②-1明星』とあるのは、3年のインターハイの府予選の団体決勝です。で、『1』のほうが、僕らのペア。3番勝負で出ていったんですが、負けました。僕はいつも3番でした。理由は?――ま、僕は性格的にプレッシャーに強かったから。『勝つときは勝つ。負けるときは負ける』と、場面場面で割り切って考えるタイプだったので」。
「中1で入部してテニスを始めました。初めは指導も優しいし、楽しい部活なのですけど、上達するにしたがって、要求は厳しく、練習はしんどくなっていった。僕ら、府予選前にやる大会で、同じ地区に上宮がいたんです。大会ごと必ず当たるので、お互いに名前も、プレーのクセも完全に覚えて戦っていました」
インタビューを受ける小市さんの手元には、取材資料であるソフトテニス・マガジンの記録ページが置かれていた。
「ここ『上宮②-1明星』とあるのは、3年のインターハイの府予選の団体決勝です。で、『1』のほうが、僕らのペア。3番勝負で出ていったんですが、負けました。僕はいつも3番でした。理由は?――ま、僕は性格的にプレッシャーに強かったから。『勝つときは勝つ。負けるときは負ける』と、場面場面で割り切って考えるタイプだったので」。
濃厚なときを過ごした中高時代。実は、入学当時は硬式テニス希望だった。明星中には軟式しかないとのことで、入ってみたら……。
「どこか軟派な気持ちだったのが、フタを開ければ『ド体育会系』。びっくりしましたね。といっても、上下関係はあまり厳しくなかったんです。高校生とも一緒に打ってもらえるし、先輩は優しかった。練習が、本当に厳しかった。真っ黒で、毎日ドロドロのくたくたになって、近所の駄菓子屋に寄って、家に帰ってからまた腹いっぱい夕飯を食べる(笑)。そんな日々でした」

優しい先輩、厳しい練習。そして、ネットのこちら側にも、愛すべき『敵』がいたという。ペアを組む後衛の同級生たちだ。
「僕は前衛だったんですが、今の子みたいにハイタッチなんてしません(笑)。ペアの後衛とはいつも意地の張り合い、ぶつかり合いでした。
『なんでそれ取れへんねん』
『お前こそ、なんでそこにいてへんかったんや』
毎日が、そんな突きつけ合い。自分がポイントを決めたときも、『後ろ』をにらみつけて『オウ、見たか』みたいな(笑)。試合で気持ちの収まりが合わないときは、その場で練習です。「お前ちょっとこっち来いや」、で、隅っこのほうで、2人でポコポコ、ポコポコ、お互い気が済むまで延々とやっていましたね。いつもその場、その場の勝負でした。
そんなふうにぶつかり合って、突きつけ合って、だからペアとは信頼関係もありました。学年の人数も少なかったし、コートの外では本当に仲が良かった。同じ代の8人、1日中一緒にいたんですもんね。実は1年ほど前、その仲間で久しぶりに会ったんですよ。もう、全然、変わらない。みんな一緒にいるときの空気が、あのころのままでした。僕も中学高校(時代)からこんなですから。楽しい夜でしたね。 中高時代のソフトテニスの恩師には、今の小市さんにも影響を与える言葉があるという。
「私が高校でお世話になった稲田尚史先生、その前の杉山末雄先生が明星でおっしゃっていたのは、たとえば『打倒、上宮』みたいな言葉ではなく、『日本一を目指せ』という目標でした。今思うと、それは大きかった。日本一を目指していれば、大阪も近畿もプロセスになる。目標は大きく掲げろ。そういう考え方を叩き込まれました」
「僕は前衛だったんですが、今の子みたいにハイタッチなんてしません(笑)。ペアの後衛とはいつも意地の張り合い、ぶつかり合いでした。
『なんでそれ取れへんねん』
『お前こそ、なんでそこにいてへんかったんや』
毎日が、そんな突きつけ合い。自分がポイントを決めたときも、『後ろ』をにらみつけて『オウ、見たか』みたいな(笑)。試合で気持ちの収まりが合わないときは、その場で練習です。「お前ちょっとこっち来いや」、で、隅っこのほうで、2人でポコポコ、ポコポコ、お互い気が済むまで延々とやっていましたね。いつもその場、その場の勝負でした。
そんなふうにぶつかり合って、突きつけ合って、だからペアとは信頼関係もありました。学年の人数も少なかったし、コートの外では本当に仲が良かった。同じ代の8人、1日中一緒にいたんですもんね。実は1年ほど前、その仲間で久しぶりに会ったんですよ。もう、全然、変わらない。みんな一緒にいるときの空気が、あのころのままでした。僕も中学高校(時代)からこんなですから。楽しい夜でしたね。 中高時代のソフトテニスの恩師には、今の小市さんにも影響を与える言葉があるという。
「私が高校でお世話になった稲田尚史先生、その前の杉山末雄先生が明星でおっしゃっていたのは、たとえば『打倒、上宮』みたいな言葉ではなく、『日本一を目指せ』という目標でした。今思うと、それは大きかった。日本一を目指していれば、大阪も近畿もプロセスになる。目標は大きく掲げろ。そういう考え方を叩き込まれました」

進学した同志社大学では、コートとは別世界に飛び込んだ。大学のOBでもあるマキノ・ノゾミ氏が主宰する劇団M.O.P.に参加。2010年の解散まで、ほぼすべての公演に参加、俳優の道を歩んでいる。
「高校を卒業したら、芝居の世界に入りたい――とは、いつからか、じわじわと感じていた思いでした。本当は大学にも入らずそのまま東京へ出て芝居をしたかったくらい。明星は進学校だったので、周りから受験を逃げたと思われるのはシャクだった。試験には受かっておいて、東京へ行こうと。そんなふうに考えていた。結局は家族に説得されて、大学は行くことになりました」
それほどまでの役者への興味は何だったのだろう。原点を言えば、子供時代の体験かもしれない、と振り返る。
「お正月、親戚が大勢集まるときに、子どもたちだけで即興の出し物をやっていて。年長のいとこのお姉さんが仕切って、役つけてみんなで芝居をする。恒例行事のようになっていました。それをじいちゃんやばあちゃんが観て、喜んでくれる。人が笑ったり、喜んでくれたりすることのうれしさ、楽しさが、自分の中に残っていたかもしれません」
演じることへの志向は、中高時代のソフトテニスと響く部分もあった。
「ソフトテニスの前衛は、まず存在感を示すことが仕事です。相手の後衛に『あいつ気になるな』『嫌やな』、そう思わせたら、もう役目は半分終わり。そういう空気とか、存在感については、コートでは常に意識していました。大きく見せるにはどうしたらいいか。あえて視界に入っておいて……とか。立ち位置や動きは理詰めで叩き込まれました。芝居でもそんな感覚は生きていると思います」
役者としての道の先で出合ったこの映画には、仕事としてソフトテニスにかかわれる喜びを感じています。苦しいこと、厳しいことのほうが多かった中学高校の部活動でしたが、今の私にとっては宝です。特にこの競技はダブルスであること、団体戦を戦うこと、大きな経験になった。佐渡では、映画の撮影の合間に、星田さんら何人かの経験者とやったんですよ、ソフトテニス。すごく楽しかった。芸能の世界でも経験者はたくさんいるから、みんなでソフトテニス・クラブをつくろう! という話も挙がっています。これはぜひ実現させたいと思っています。
ソフトテニスは苦しくて、厳しくて、本当に楽しい。そして私の宝物になりました。皆さんも楽しんで頑張ってください。
「ソフトテニスの前衛は、まず存在感を示すことが仕事です。相手の後衛に『あいつ気になるな』『嫌やな』、そう思わせたら、もう役目は半分終わり。そういう空気とか、存在感については、コートでは常に意識していました。大きく見せるにはどうしたらいいか。あえて視界に入っておいて……とか。立ち位置や動きは理詰めで叩き込まれました。芝居でもそんな感覚は生きていると思います」
役者としての道の先で出合ったこの映画には、仕事としてソフトテニスにかかわれる喜びを感じています。苦しいこと、厳しいことのほうが多かった中学高校の部活動でしたが、今の私にとっては宝です。特にこの競技はダブルスであること、団体戦を戦うこと、大きな経験になった。佐渡では、映画の撮影の合間に、星田さんら何人かの経験者とやったんですよ、ソフトテニス。すごく楽しかった。芸能の世界でも経験者はたくさんいるから、みんなでソフトテニス・クラブをつくろう! という話も挙がっています。これはぜひ実現させたいと思っています。
ソフトテニスは苦しくて、厳しくて、本当に楽しい。そして私の宝物になりました。皆さんも楽しんで頑張ってください。
Text by 成見宏樹
Photo by 小山真治
Photo by 小山真治